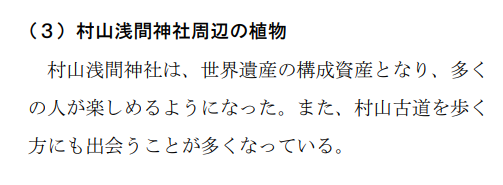博物館構想を考える上で「富士宮市の通史的性格」からも考えていく必要性があると感じ、また「
(仮称)富士宮市立郷土史博物館基本構想検討委員会」の資料については未だ言及していなかったため、これらも併せて「富士宮市の通史的性格と博物館構想」をテーマに解説していきたいと思う。
富士宮市の歴史を俯瞰して見てみると、非常に歴史トピックに恵まれた地域であるということが分かる。例えば「日本三大仇討ち」にも数えられる「曽我兄弟の敵討ち」は富士宮市で起こったことであるし、それに付随して富士宮市を舞台とする「能」「幸若舞」「浄瑠璃」作品も成立した。また富士宮市の地名を冠する史料『富士野往来』は江戸時代の教科書としても用いられた。あらゆる「表現」の中に組み込まれたのである。
(小井土2022;p.480)は『曽我物語』を説明する中で「霊峰富士を背景に、物語が大団円を迎えているということこそが、この物語が持つ何よりのポテンシャルと言えるのではないだろうか」と述べているが、やはり富士山麓という土壌は大きく関係するように思う。
単一の事象で言えば「富士大宮楽市令」は全国で用いられる高校日本史の参考書にも記されており、古文書学では法制史学の分野で特に用いられる。ちなみに高校日本史の参考書には富士宮市の事柄として他に「富士金山」が記される。
また絵画化例も極めて多く、『曽我物語図屏風』を始め「武者絵」も富士宮市を描いたものが多い。特に前者が作成され続けた背景については(小口2020)に詳しい。富士の巻狩を描いた図が地方にも伝搬していた事実等から(中澤2022;p.105-107)は「富士の巻狩のイメージが、地方の武士たちにも共有されていたことをよく伝えている(中略)戦国期に曾我物が百姓にまで広く流布し、富士の巻狩が東国の王の壮挙として語り継がれていたことを如実に示している」と説明する。また(中澤2020;p.121)にもあるように、外国人(フロイス)ですら富士の巻狩は知り得ていたことであったし、ジョアン・ロドリゲスも知っていた(『日本教会史』)。他、「富士参詣曼荼羅図」もある。あらゆる分野において輝いたものがある。
富士宮市という地域は時代を問わず、常に人々に意識されてきた地域なのである。ここまでの規模感を有する地域は、日本でも指折りかと思う。例えば曽我物を演じる時、その担い手は富士野の地を強く意識したことだろう。それは観る側も同様である。人穴探索を題材とした武者絵も多いが、この場合は奇怪な事が起こる地として描かれていたので、人々はそれらを見て恐ろしいイメージを膨らませていたに違いない。実際『驢鞍橋』や『文武二道万石通』にはそれが反映されている。『富士野往来』で学習する子どもたちは、強く富士野の地を想像したことだろう。
従って「富士宮市の事象が歴史の中にもたらした影響」を人々に説くことが極めて重要なのである。ところで「第3回(仮称)富士宮市立郷土史博物館基本構想検討委員会」にて以下のような意見があった。
この指摘は極めて重要であると思う。そしてその答えは上で記したように
"富士宮市の事象が歴史の中にもたらした影響"を人々に説く
としておきたい。私は展示の方法は「①外(影響を長く及ぼしたもの)と②内(内政)」の2つがあると考えており、そのうちの①が上である。
しかしこの恵まれた環境下において、それらが富士宮市民の中で殆ど浸透していないとすれば、それは穏やかではない。その場合その要因の一端、いや多くは行政側にあるのではないだろうか。行政側は世の中の様々な事象に対する感度も低いと思われる。
例えば文化庁選定「歴史の道百選」の「みのぶ道(93番)」に富士宮市が含まれていないのはおかしいと気付かなければならない。何故なら、身延道は富士宮市を通っているのだから。駿州往還は富士宮市内房を通過しており、これは紛れもなく「みのぶ道」である。また富士吉田口登山道(37番)は選定されているのに富士宮市の登山道が含まれていない理由も考えなければならない。要は、ロビー活動が全くないからである(これまで)。普通に考えて、そんなところが人を呼び込める博物館など作れないだろう。博物館や企画を認知させる手法は、結局のところロビー活動に類するものなのだから。
富士宮市の歴史のフラッグシップ的存在として「富士氏」が挙げられる。(前田1992;p.83)に「従来、史料の量に比べて研究成果が乏しかった武田氏と大宮との関係を自分なりに探ってみた」とあるように、富士氏の動向を示す史料は新出史料を含めそれなりにある。前田氏のそれは、研究を大きく進展させたと言えるだろう。
史料の残存量もそうであるが、富士氏の歴史上での存在感を考慮すると、あまりにも知名度が不足しているのではないだろうか。富士氏は室町幕府の在国御家人で、富士城の城主であったのだから。正直「富士宮市はこれまで何をしていたのだろうか?」と言われても仕方がない。
「国立歴史民俗博物館」の2018年の企画展「日本の中世文書―機能と形と国際比較―」にて「沙弥道朝書状」という古文書が展示された。その文書は富士忠時が受給者であるが、不思議なことに解説では富士氏には全く触れられていない。また『浅間大社遺跡 山宮浅間神社遺跡』(2009)という、静岡県埋蔵文化財センターによる報告書がある。報告書内に「浅間大社年表」というものがあるが、「富士大宮司氏」や「富士大宮司内分裂」といった意味がよくわからない用語・文章が連なっている。
しかし富士大宮司というのはその時ただ1人だけであって、しかも富士氏の当主が名乗る神職名であるので、「富士大宮司内分裂」とか「富士大宮司氏」などという概念は存在し得ない。富士大宮司は富士氏の一側面にしか過ぎないのである。『富士大宮神事帳』という史料があるが、この史料1つだけ見ても、「富士兵部少輔」(富士大宮司)「富士常陸守」「富士又七郎」「富士左衛門」の人物が見え、多層的である。
これらを見ると富士氏に関連する論及は、単一レベルでは優れたものがあったとしても、全体としては恵まれたものではなかったことが分かる。県内の組織の報告書であっても、そのような状況であったのだから。そしてその期間は永きに渡るものであった。その背景は一体何だろうか。富士宮市のHPや刊行物を見ると、やはり「富士氏=富士大宮司」という捉え方をしてきた節がある。"〇〇は富士大宮司に関わるものと考えられる"といった文脈も度々見られるが、では何故他の富士氏の人物ではなく富士大宮司であると考えるのかといったことについては、全く触れられていない。本当に近年まで、富士宮市の歴史研究の成熟度は相当低いところにあったと言う他ない。
逆に近年(ここ10年)は富士宮市からの目を見張る成果・展開があり、従来と対比すると一層際立ってくるように思う。それは内部構造が変化したからに他ならない。今すべきことは、学芸員の方々が研究活動等に集中できる環境を整えることではないだろうか。
また今年は富士宮市の歴史に関する報告が多く世に放たれた年であり、注視していた人であれば確実に感知できたことであろう。これほどまでに重なるのは珍しいことである。『戦国武将列伝 6』(6月)には富士信忠の解説が収められ、『室町幕府と東海の守護』(8月)にも富士氏に関する論考が認められ、特筆すべきは9月発刊の『領主層の共生と競合』(2019年のセミナーを原型とする、『静岡県地域史研究』にも一部所収)であり、この一冊は極めて重要な意味を持つ。説明会に出席した一般の人々の中でこういう動向を感知できた人がどれくらい居るのか、興味深いところである。博物館構想の説明会であるのに全員が感知できない層であったのなら、それはただ単に富士宮市の人材不足と言えるのであり、それは富士宮市にとっての不幸と言えるのではないだろうか。
これまでの研究の蓄積不足は否めないところであり、これは博物館構想にとって致命的な枷となるだろう。それを一気に飛び越えるエネルギーは、相当なものとなる。それを現在就いている学芸員の方々に一直線に強いるのは不憫な話と言えるのではないだろうか。したがって、以下の意見を支持したいと考える(第2回会議録・第3回会議録より)。
また博物館建設には一般市民側の意欲も必要である。換言すれば「富士宮市民のアイデンティティが必須」と言える。その形成のための取り組みが、全くなされて来なかった。
「富士宮市の領主は"富士さん"でした」とか「富士宮市はあの「楽市」が行われた場所です」といったことを何故言ってこなかったのだろうか?他の地方自治体はもっとアピールしているではないですか。楽市が「富士宮市の歴史年表」の類に従来まで記載されていなかったのは、その証左であろう。また以前例を挙げたが、TV等で頻繁に「近年村山口登山道が発見された!」と明確に誤った情報が流布されている。その度、私はこう思う。
本来こういう時に富士宮市民から「20世紀には調査も実施され、以前より認識されてきたものであり、TVは間違っている」というような声が聞かれるべきなのではないか
悲しいかな、村山の人々ですら分かっていないようである。また「富士宮市の自然(第五次富士宮市域自然調査研究報告書)」に以下のような箇所がある。
多くは言いませんが、富士宮市の公式資料でこれとは、なんと情けないことか。実は何故か歴史史料で多く確認される「村山口」の文言をどうしても用いたくないという勢力が居る。また学術用語としても「大宮・村山口登山道」があり、その点からも不可解である。
そして村山口登山道のガイドも数多く居るようであるが、根本的なことを理解していない。おそらく多くの人は「古の登山道を登ってみたい、でも地理的な知見がなく難しい」という純粋な思いから登山のガイド依頼をするのであろう。そしてその登山道とは「大宮・村山口登山道」のことなのである。しかしその気持ちを全く汲み取らず、何故か「村山道」を案内するガイドも居るようである。もっと酷い場合は、更に下から誘導しているようである。そもそもガイドは「大宮・村山口登山道」と「村山道」の違いも分かっていないように見受けられる。ちなみに「村山道」に関しては史料上用いられた記録は殆ど無く、成立も近世である。
するとどうであろう。一念発起し、おそらく人生一度切りという思いから登拝したのにも関わらず、後で全く異なる道を歩かされていたことに気づくということになる。これは依頼主への裏切り行為ではないだろうか。また「村山道」を望んでいたのに「大宮・村山口登山道」を案内してしまっていたら、それはそれで危険である。難易度が桁違いであるからだ。つまりこの用語を理解していない人というのは、依頼人を危険に晒す可能性を十二分に持ち合わせているのである。ガイドとして失格であることは言うまでもない。これらの事例を見ても、一般の歴史認識は相当に弱い。
しかし学術的な視点で真っ当に動いている組織は、この点をしっかりと把握して動いてくれていることを私は知っている。そして私は、それを本当に誇らしく思う。1993年には村山口登山道に関するまとまった報告書を出していることも知っている。もっと自分たちから成果を目に見える形で表してもよいのではないだろうか?
勿論基本的にはガイドの不勉強が問題ではあるのだが、やはり行政側からも「これが①大宮・村山口登山道、これが②村山道、①と②は違います!」とハッキリとした分かりやすい提示をするべきなのかもしれない。そしてまとまった形の学術的な調査は1993年のものを嚆矢として、その後も重ねて調査が行われ、概ね全容が明らかとなったという文言を付け加えておくべきだろう。そしてこれは静岡県・富士宮市・富士市の共同で行うべきだろう。TVおよびガイドの不勉強の尻拭いでしかないのは分かるが、考えなければならない。歴史学は、こういう啓蒙活動もセットであるべきなのかもしれない。
つまるところ、単純に認知が絶望的に足りないのである。それは市HPのコンテンツからも見て取れる。富士宮市HPの歴史コンテンツを確認してみたところ、以下のページのみであった。あとは企画展の紹介ページのみである。
正直、これらのページはあまり意味を持つものではない。専門性の高いコンテンツは、市HPには不必要なのである。それは学術の場でなされていれば良い。そうではなくて、富士宮市の代表的な歴史トピック・名称を題したページを10程作成するだけで良いのである。本当に簡単な話なのであるが、それが出来ていない。なので検索に一切引っかからないのである。
「富士宮市の領主富士氏について」「井出正次について」「富士郡の要害大宮城について」等と題したページを作って、簡単な解説を加えれば良いだけの話なのである。それが何十年と出来ない。何処でもやっていることなので、本当に不思議である。ところで、以下のような意見があった(第3回会議録)。
これはタブレットに富士宮市HP(歴史のページ)へリンクするタブ等を設ければいいだけの話なのである。従って、そのページをまず作成する必要性がある。それを氏は述べるべきなのである。
基本的に今求められるのは「富士宮市の代表的トピックのページ作成+それを流布する力(ロビー活動)」である。これまでの蓄積不足は甚だしい。仮にしっかりと取り組みがあれば、富士宮市に現在「楽市通り」(道の通称)があったと思うし、富士宮市の「市の木」はシュロであったに違いない。普通に考えれば、これらを制定すべきなのである。
また「富士山女子駅伝」でもその道を用いているのに、何故「楽市通り」と喧伝しないのか。富士市はもっとやっているではないですか。
上の画像は富士山女子駅伝のコース紹介であるが、「富士山しらす街道」と記されている。そして放送でも呼称されている。この種のものこそが「ロビー活動」であろう。
また認知度さえあれば「富士海苔」も保護のための機運が高まって「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)に登録される段階にまで漕ぎ着けていたかもしれない。そして何よりも、博物館建設の機運は今よりは高いものとなっていただろう。つまり博物館を建設できない要因の1つは、何を隠そう「(策定している)内側の姿勢」にあったのである。
10年とか20年といった年月をかけてゆっくりと浸透させていくべきアプローチが殆ど確認されない。体感的には少なく見積もっても20年、厳しい言い方をすれば30年くらい遅れている感じがする。もちろん市民側の閾値の問題もあるだろうが、何でもかんでも市民のせいにしてはいけない。
ただ富士宮市民のせいである部分も過分にある。「
富士宮市郷土史博物館構想に賛成・反対か、本当の問題点を考える」等でつらつらと富士宮市民の気質等について言及しているのであるが、要はこの中の登場人物は
世間知らずなのである。説明会というのは、実質"行動力のある世間知らず"が場を乱しているだけの場になっているのである。そこにファクトは無い。
そもそも大人たちこそ子供を見習うべきではないだろうか。子供たちの方がよっぽど生産性がある活動をしている。例えば「全国高校生歴史フォーラム」では富岳館高校の学生が「富士氏による富士宮地域の支配とその性質の変化~富士山本宮浅間大社大宮司・富士氏の盛衰に着目して~」という研究を発表している。
これを成立させるためには「①調査→②理解→③形にする→④発表」という過程が必要である。多くの大人は出来ないことである。まず①の段階で殆どの大人が出来ないであろう。
また「静岡学園高等学校歴史研究部」も富士氏に多く言及した論考を出している。
富士宮市民なのに永きにわたり領主であり続けた富士氏すら知らないのは、この際良いとする。しかし大人として、この種の活動に支障がない体制をなるべく整えてあげようという気概くらいもったらどうだろうか?
むしろこの種の活動を促進させたいとは思わないのだろうか?説明会に行って「廃校!廃校!」と理由のわからないことを述べるエネルギーを、もっと違う形で活用した方がよっぽど生産性があるだろう。
そもそもこれまで文化課等で費やした費用なんぞとっくにペイできているのである。「富士宮市郷土史博物館構想に賛成・反対か、本当の問題点を考える」で記したように世界文化遺産「富士山」の構成資産は研究の有無によって左右されている。普遍的価値はイメージで決定されるのではない。
そして構成資産であるという付加価値が、観光客を更に呼び込んでいるのである。その経済効果は計り知れない。むしろ博物館がありもう少し研究が深化していたら、もう1つくらい市内に構成資産はあったかもしれない。私がみる所、富士宮市内はあと1つは望めたところだろう。
そもそも「お金」という視点でこの種の話をすることがナンセンスなように思えるのであるが、説明会の質問では「お金」というワードが頻出しているのも事実である。その上で貴方がたが好きな土俵で論じたとしても、正直全くお話にならないというのが実情であろう。
ここで少し角度を変えてみよう。大発見とされる「銅造 虚空蔵菩薩像 懸仏(1482年)」は富士山頂の三島ヶ岳で発見され、現在富士山本宮浅間大社に奉納されているが、発見の経緯が面白い。遠藤秀男『富士宮歴史散歩』には以下のようにある。
横浜の人が突然私のところを尋ねて来て「山頂でこんな物を拾ったが見て欲しい」という。見ると円盤型の青さびた掛仏である。(中略)そして左右に文字が刻まれていて、「文明十四年六月」「総州菅生庄木佐良津郷」とあり、(中略)千葉の人によって富士山頂に奉納されたものであることが判明した。(中略)発見のきっかけは、次のようだという。拙著『富士山の謎』で富士山中から古銭が多く発見されている話を読み、登山の折りに注意して歩き、(中略)砂中に埋まっているのが見つかったという。そこで私の所へ持ち込んだという次第であるが…
つまり「書物」の存在が無ければ見つかっていなかった可能性もある。このように世の中のものに感化され、実際に行動を起こし、何らかの成果物が生まれるという過程がある。博物館の企画展なども大きく人々に影響を与えるだろう。もっと大きく言えば、有史以来の偉大な発明も、全くの土台無しで成されたものは無い。こういう個々の情熱の積み重ねが世の中を動かしてきた。こういうものが最終的には次の活動に繋がっているのは間違いない。博物館はここで言うところの「土台」だろう。
しかし個々の経歴など事細かく追跡できようもないから、定量化はできない。例えば10億の経済効果があったとして、「〇〇さんの活動が〇〇円寄与した」などと言うことは物理的に不可能なのである。つまり説明会の質問者というのは、定量化ができないことを良いことに、好き放題言っているだけでしか無いのである。
上は富士宮駅伝競走大会のチラシである。こういう大会は、何の資金もなく開催できるわけではない。スポンサーが居るからなし得るのである。
それと同じように、構成資産があるから観光という「産業」が成り立っている部分もある。それを成立させたのは「研究量」であり、その立役者は研究者である。既にあるものに付加価値を付けたということもできる。でも研究者らは"私達が付加価値を付けました"なんて言わない。なぜならあくまでも"研究者"だからである。しかし外野は少しくらい感知できなければならないし、それすら感知できないのであれば問題である。
私は博物館構想を考えていく中で、多角的に思考を巡らせてみた。例えば富士市立博物館建設時の過程も調べてみたし、上にあるように富士宮市民の気質にまで考えを及ばせてみた。やりすぎなくらい多角的に考えたように思う。
これまで様々な思考を巡らせ、そして途方もなく多くの史料・資料にあったように思う。そして導き出した博物館の姿が、以下である。
| 項目 | |
|---|
| 名称 | 「富士博物館」が基本と考えるが、少なくとも「郷土史博物館」でなければ良いという印象もある。名称の競合を防ぐため「Mt.FUJI ミュージアム」も良いと考える。 |
| 外観・内装 | 『築山庭造伝』に図示される富士大宮司邸(茶庭・大書院)を模したものが望ましい。空間からデザインする必要性がある。建物自体が展示物であってほしい。博物館の「緑」を担う場所にもなる。 |
| 展示内容 | 【外】(影響を及ぼしたもの) |
| | 富士宮市を舞台とする芸能を紹介する(「曽我物(能・幸若舞等)」) |
| | 富士宮市を舞台に含める物語・教科書を紹介する(『曽我物語』『富士野往来』『富士の人穴草子』等) |
| | 富士宮市を舞台とした絵画化例を紹介する(「曽我物語図屏風」「武者絵」「富士山登山絵図、特にかぐや姫との関連について("外"ではなく"内"であるがここに含めた)」) |
| | 関東の富士家(江戸幕府旗本)や井出家(江戸幕府旗本)を紹介する |
| | 【内】(内政) |
| | 富士宮市の領主「富士氏」を通史で紹介する |
| | 富士宮市の在地勢力「井出氏」を紹介する |
| | 大宮城について解説する |
| | 富士野を巡る事象について解説する |
| | 富士海苔について解説する |
| | 富士川との関わりについて説明する(「富士山木引」等) |
上を成立させるには、まだまだ研究が足りない。例えば人穴は恐ろしい地であると広く認識され、それは『驢鞍橋』や『文武ニ道万石通』等からも垣間見える。そして仁田忠常の人穴探索を題材とした武者絵も多い。これらの系譜を追った論考も未だにない。勿論発端は『吾妻鏡』であるが、経時的に整理していく必要性がある。人穴は相当に知名度が高かったと考えられる。
そもそも「曽我物」を富士宮市の視点から論じたものがほぼ皆無であるように思う。何故だろうか。例えば能〈伏木曽我〉は完全な富士宮市が舞台の能作品である。そしてこの作品を復曲する活動があり、先日無事に上演された。こういう活動を富士宮市民が全く感知していないというのは、なんとなく寂しいものがある。こういうものを感知できる人間が、博物館についてどう考えるのかということに私は関心がある。
〈伏木曽我〉は(竹本2021;p.36)が「作風が他の曽我物と全く異なり、表現も洗練されている」と評しているように、完成度が高い。典型的な修羅能であるのにも関わらず、そこには「怨」がない。
『曽我物語』を一から解説するのは難しいが、〈伏木曽我〉に対応する『曽我物語』の箇所を引き合いに出して互いに解説することは十分に可能であり、そして分かりやすい。曽我の伝承は事細かに説明するのは難しいが、富士宮市を主体として表現する場合は『曽我物語』(特に真名本)〈伏木曽我〉『富士野往来』の三点を引用し、対応する箇所を比較して時系列で説明するのが一番良いように思える。博物館は表現方法に一番拘るべきである。
そもそも博物館法によると、博物館は以下のように定義されている。
この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法による公民館及び図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)による図書館を除く。)のうち、地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第二十九条において同じ。)を除く。)が設置するもので次章の規定による登録を受けたものをいう。
私はここにある文言で言えば「芸術」にも関心を寄せる必要性があると思うし、それ故に絵画化例を引き合いに出している。また富士海苔や富士山木引は「自然科学」の方面からも迫ることができよう。材料は常にそこにあるのである。
富士宮市の地域内の事象だけに囚われるのではなく、富士宮市を舞台とした芸能・作品にまで考えが及んだ博物館であれば、より人を巻き込むことができるのではないだろうかと考える。まずはロビー活動の徹底的な強化が求められる。
- 前田利久(1992)「戦国大名武田氏の富士大宮支配」『地方史静岡』第20号、地方史静岡刊行会
- 小口康仁(2020)「「曾我物語図屏風」の展開―富士巻狩・夜討図から富士巻狩図へ―」『國華 第1496号 第125編 第11冊』
- 竹本幹夫(2021)「『曽我物語』と曽我物の能」『能と狂言 19』、能楽学会
- 小井土守敏(2022)『曽我物語 流布本』、武蔵野書院
- 中澤克昭(2022)『狩猟と権力―日本中世における野生の価値―』、名古屋大学出版会